9
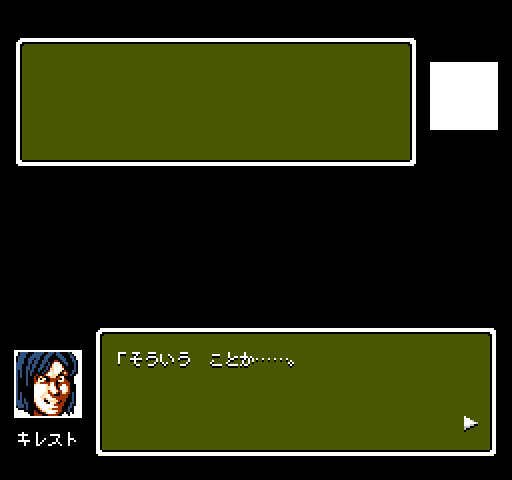
何故だ。何故再侵攻を読み切ったように罠がしかけられている。晋陽の情報は徹底して秘匿した。方針もこの場で修正をかけた。なのに何故悉く打ち破られる。自分達は常の通り行動していたはずだ。
なのに、何故?
「そういう、ことか……」
怒りに任せて拳を振り下ろす。WDの重量にも耐えられるはずの机が真っ二つに折れた。先程やりこめられた理由は、ただの油断だと思っていた自分がどんなに甘かったか、今気付いたのである。キレストはその視界の端で通信兵が立ち尽くしているのを確認し、自らの過ちと辿り着いた答えが正しいことを悟った。
/ ※ /
「でだ、あいつらは正直、これが演習だと心の底から思い込んでいる。だからどんなにやられても本気にはなれない。いいとこ『さっきより気をつけてゆっくり行こう』ってなもんだな」
エフナーは赤いマグネットの半分を手に取った。先程と同じ様に等間隔で図の上に貼り付けていく。「なので、こんな感じでもう一回攻めてくるはずだ。だもんで、ここ」
そう言ってマーカーで図の中央に線を引く。「ここに、どばーっと罠をしかける。と言っても、デストラップはダメだかんな」
工作担当の第2小隊が不満げにうぇーいと声を上げる。殺さず、と言うのは敵が強ければ強い程面倒なのだ。「せんせー、材料はどうすりゃいいんすかー」
「演習場にあるものでどうにか、と言いたいところだが、今回は特別にこんなものを用意しました!」
エフナーが目配せして、あるものを持って来させる。テスト用のWD装甲と白いシートだ。俄かに場がざわつく。装甲は分かるとして、シートの意図が読めない。見た目にはただの白いシートだが、持って来させた本人はそれを非常に慎重に扱った所がまた不可解だった。やたらとニヤけているのがまた怪しい。
「何すか、それ」
「んっふっふー、これはだなぁ、こういうもんだ!」
ほわー! と気合いを込めて装甲を白いシートに叩き付けるエフナー。皆が固唾を飲んだ。これで何が起こるというのか。エフナーはもう一度ニヤリと笑うと、叩き付けた装甲をそのまま持ち上げた。いや、装甲だけではない。シートもそれに付いている。おお? と感嘆の声が漏れた。これはなにかしらの新素材なのか? そんな期待が場に満ちる。
「ということで見ての通りトリモチです」
『わっかんねーよ!』
全員でツッコミを入れる。一人だけ第4小隊の隊長だけが『だから受けないって言ったのに』と深く溜め息をついた。その辺りは意に介さずエフナーは続ける。「何でも宇宙開発の副産物らしくてな、余ってるから使えって上に言われたんよ」
「性能はどうなんすか?」
「バッチリだ。天陽着て上で体育座りしたら取れなくて、そのまましくしく泣いたくらいだ」
「晋陽にも通用するんすか?」
「多分な。最悪無理矢理引きちぎることも可能かも知れんが、時間はかかるだろうからその隙に押さえちまおう」
一通り質問して満足したのか、うぇーいと同意の声が挙がる。その中で一つだけ手が上がった。「どしたね第2小隊くん」
「設置するのはいいとして、どれくらいあるんですか、それ」
「ここ20部屋分くらいかな」
「その線上全部には足りないっすよ」
「だろうから、あいつらを誘導する。それでも足りなきゃ別の罠だ。どちらにせよ天陽をマネキンに着せるかなんかしたら騙されるだろ。その辺は任せる」
「うす」
「あー、そうそう。道を塞いだり落とし穴掘ったりはやっていいらしいぜ」
「マジすか。腕が鳴りますよ」
「おう、やったれやったれ」
まるで部活の会合の様である。ただ一つ彼らの後ろで重機の手配を始める部下たちの姿がなければ、だが。「さて」
エフナーが、手を叩きながら皆に呼びかける。一瞬にして先程の弛緩した空気が引き締まった。ここからが本題なのだ。「ここまでで敵の3分の2を制圧したわけだが、諸君の中に疑問を持った者もいるだろう。最初からでも、途中からでも、敵がなりふり構わず突撃してきたら? とね」
ホワイトボードに残った赤いマグネットを一つ一つ取っていくエフナー。動作は非常に緩やかで、何かを考えているようでもあった。「今まで説明しなかったのは、する必要がなかったから。言っちまえば、いつ突撃という手段をとってこようと、こっちがやることは同じでいいのよ」
俄かに場がざわつく。長くエフナーの下で戦っていても、この様に彼が話すのは初めてのことであった。それだけ楽な戦いってことだと、エフナーは一人思った。言う必要もないけどな。「いつ突撃されてもする事は一つ。自陣に向かって走って集合。んでもって防衛。こんだけだな」
「いつでも、って、最初の段階でも?」
「モチロン。まぁその時はこっちがバラけてるから、その辺は工夫するけどな。ただ、基本は同じだ」
先程までとは異なったざわつきが広がる。いくら何でも無謀だと皆が思った。その中でエフナーだけが笑った。「戸惑うのもわかっけどな、とにかく本部からありったけの晋陽を吐き出させりゃいいのよ。その間に俺が頭を狩る」
「俺がって言いますけど、どうするんすか? 晋陽の直中を越えていくわけじゃないんでしょ?」
第3小隊の隊長が皆を代表して問いかける。エフナーの策はまるで『ずっと一緒に待機している』かのような気軽さを含んでいた。相も変わらず笑いながら、エフナーはペンを手に取った。「ああ、俺と第4の待機場所書くの忘れてた。ここだから」
ホワイトボードに印されたそれは、何度目か分からないざわめきを生み出した。